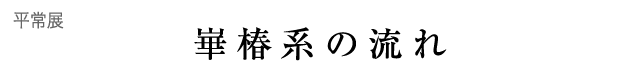
| �J�� | �F | �����R�O�N�Q���R���i�y�j�`�S���P���i���j |
|---|---|---|
| �J�َ��� | �F | �ߑO�X���`�ߌ�T���i���ق͌ߌ�S���R�O���܂Łj |
| ��� | �F | ���ʓW���� |
�n�ӛ��R�ƒ֒֎R�͎t��̊W�ɂ���܂��B���̓�l�ɂ��A�e������������ƒB�́u���n�v�Ə̂���܂��B��������̒����܂Œ֎R���炻�̉�n�͒��ړ`���A����H�J���珼�ьj���ɂȂ����Ă��܂��B
| ���ʓW���� | ||||
| �w�� | ��i�� | ��Җ� | �N�� | ���l |
| �O�g�u | �n�ӛ��R | �����N�� | ||
| �ݗ����]�� | ���|�� | ����11�N(1878) | ||
| ����t����� | �����ؗz | ����43�N(1910) | ||
| �_�Β� | �勴���� | ����40�N(1907) | ||
| �ԙ��� | ����H�J | ����18�N(1885) | ||
| ���D�@��C���啶�l�@�����n | �R���\�����������@���� | ���� | ���\�y�����ف@�����F�F�L�O�@�R���\�����������@�� | |
| �s�� | ���A�} | �n�ӛ��R | �����N�� | |
| �n���} | �n�ӛ��R | �V�۔N�� | ||
| ���Ԑ} | �֒֎R | �V��4�N(1833) | �l�� | |
| �t�]�R���} | ���c���� | ����5�N(1858) | ||
| �����} | ���c���� | �V��11�N(1840) | �l�� | |
| �����P���V�} | ���䌰�� | �Éi2�N(1849) | ||
| 莉ƑS�c�} | ���c_�� | �O�����N(1844) | ||
| ���ߔV�} | �����t�� | �]�ˎ����� | ||
| ��i�R���} | �֓����� | �V��9�N(1838) | ||
| ���v�}��� | �i�����R | ���v���N(1861) | ||
| ���ĎO�F�} | �n�Ӕ@�R | �V�۔N�� | ||
| �֎}�} | �։ؒJ | �O��3�N(1846) | ||
| ���O�q��L�} | �։ؒJ | �Éi2�N(1849) | ||
| ���Ԑ} | ���ѐ�� | ���a29�N(1954) | ||
| ���x(���ѐ�呜) | ����p���Y | ����43�N(1910) | ���і����� | |
| ����ꐆ�} | �n�ӏ��� | ����15�N(1882) | ||
| �ԙ��} | �n�Ӊؐ� | ���a����O�� | ||
| ���o���V�} | �֓�R | ����27�N(1894) | ||
| ���O�V�} | ���ьj�� | ���a����O�� | ||
�����Ԓ��A�W����ύX����ꍇ���������܂��B�܂��W�����͍�i�ی�̂��߁A�Ɩ��𗎂Ƃ��Ă���܂��B���������������B
�� �n�ӛ��R�@�����T�N�i1793�j�`�V��12�N�i1841�j
���R�͍]�ˍ����c���ˏ㉮�~�ɐ��܂ꂽ�B�G�͋��q���˂���J����ɂ���l����R����łͤ���m�I�ȉA�e����߉�@��p������{�G��j�ɂ��傫�ȉe����^�����B�V�ۂR�N�40�Ŕ˂̍]�ˉƘV�ƂȂ褍�������ˍ����̗��Ē����ɓw�߂Ȃ��礖����̌����̒��œ��O����悭��������]�˂̗��w�����̒��S�ɂ��������؎Ђ̍���ō��쒷�p��Ƌ��ɓ������ꤍݏ�孋��ƂȂ����B���q�������G�褉��t�̐��v���~�����Ƃ�������˓��O�̐��]�ɂ�褔ˎ�ɍЂ��̋y�Ԃ��Ƃ������ꤓV��12�N�ɓc���r�m���Ŏ��n�����B
�� ���|���@����11�N�i1814�j�`����19�N�i1886�j
���͗ߓ��A���͋G���A�ʏ̂������Ə̂��B�V��10�N(1839)����12�N�ɂ����Ē����s�c�������̉Ɛb�Ƃ��Ē���ɑ؍݂����B����؍ݒ��ɂ́A�C�p�������H��(1798�`1866�j�Ɋw�B�V��12�N�T���̏H���̓��ۃ����ł̖C�p���ˉ��K�ɂ��Q�����Ă���B�؎Ђ̍��ȑO�ɓn�ӛ��R�ɂ����̂����A���ߒJ����(1763�`1840)�ɂ��A���̌㛺�R�ɂ����Ɠ`�����邪�A�ڍׂ͕s���ł���B�o�j��单�~�B(�单�������v�̒��j�A1797�`1851)�Ɋw�ԁB�H�����^���Ɋ������܂�đߕ߂����ƁA�|��͎���̖��͂�Q�����B�Éi�Q�N(1849)�����S���Ȃ�ƁA�Ɠ��p���A����Ƃ̗p�l�ƂȂ����B�������N(1864)�ɂ͉Ƃ��q�����Y�ɏ����đމB�B���C�R�l�ɂ��Ď����Ղ��K���B�����ېV��A���劁�쎁�̐��������̘b���A��������Ղ����ɑւ����쎁�ɑ������B���̒����̕]�Ɉ˗������ґ����A�Ƃ̘b���`���B�ӔN�͓����ɖ߂�A������J�ŗ]���𑗂����B�V�۔N�Ԃ̓��L���_�ˎs�������قɏ�������Ă���B
�� �����ؗz�@�����V�N�i1824�j�`�吳2�N�i1913�j
�l���S�����n�Q�ɑ㊯���c���\�Y�̎O�j�Ƃ��Đ��܂�A���𐳖��A����و��A�ؗz�E�s�x���ƍ������B�]�˂ɏo�Ċ��w��勴�c���ɁA�������H�ɁA����O�����N�i�P�W�S�S�j����֒֎R��m��ؓ��Ŋw�ԁB���Z�͑㊯�Ζ������Ȃ���A������A���ƍ������B�]�˂���߂�A�g�c�i���L���s�j�̌������ޗlj��̒����Ƃ����A�앺�q���P�������B�p�ˎ��͎m���ɗ��A�����ېV��A�ƋƂ��q�ɏ���A�����E�擹����Ƃ��������ł������B�����P�V�N�i�P�W�W�S�j�̑�������G�拤�i��ɏo�i�A�����R�O�N���A�_���ƂȂ�A�����_���Ђɂ�20�N��d�����B
�� ����H�J�@����10�N�i1827�j�`����31�N�i1898�j
�]�ˌ���\��������̓��{��ƁB����10�N1��7�����܂�B�֒֎R�Ɏt�����A�Ԓ���ӂƂ����B�Ď��ӌ��̐��i�ł������B�₦�đe�\�̕��Ȃ��A���l�搊���̌�Ɏ���Ă��A���̗_�͒Ă����A��𐿂��҂͂��������B����26�N�鎺�Z�|���B����31�N6��26�������B72�B�]�ˏo�g�B���͑��B�ʏ͖̂��V���B��i�ɢ�|�ΐ}���e�Ԍ{�}��ȂǁB
�� �勴�����@�c�����N�i1865�j�`���a20�N�i1945�j
���́A���̓Ɠ��̌Ղ̊G�ɂ��u�Ղ̐��v�Ƃ��Ēm���A���̔ӔN�ɂ͒����̉�d�Ɖ���W�������Ȃ������ɂ��ւ�炸�����於���ւ�����ƁB�A��_�ɐ��܂�A�c������G���D�݁A�n���̓��ƁA�˓c�ܓ��ɂ��ĊG�̎�قǂ����A18�̎��ɋ��s�ɏo�Ĉꎞ���֒֎R�Ɏt�������V����فi1824�`1895�j�Ɏt�����A�̂����R�̓�j�ł������n�ӏ��i1835�`1887�j�ɓ����Ŏt�����ĎR���Ԓ��̊�b��g�ɂ���B1895�N�A��4��������Ɣ�����Ɂu�Ր}�v���o�i���A���o�i�Ȃ���J��E��v���l�������̂���ɁA�e��W����Ŏ�܂��d�˂Ă���B����33�N�i1900�j�ɂ̓p������������Ɂu�ҌՐ}�v���o�i���A�����̉�Ƃ�}���ē��{�l��ƂƂ��Ă����P�l�D�܋��v����܁B�����ăZ���g���C�X����������i1904�j�ŗD�܋��v�A���p������i1910�j�ł����v����ȂǁA���O�̔�����Ŏ�܂��d�˂��B�@���a5�N�i1930�j�́w���{��ƕ]�������֗��x�i���{�G�挤����j�ł́u���ʓ�����Ɓv�Ƃ��ĉ��R��ρE�|�����P�ɕ��ԕ]�����Ă���B
�� �֒֎R�@���a���N�i1801�j�`�Éi�V�N�i1854�j
���͕J�A���͓ĕ�A�֎R�E��ؓ��E�x���ȂǍ������B�]�˂ɐ��܂�A���Ɠ��������{���g���S���߂�ƂƂ��ɁA��ƁE�w��ɗ�B���R�s���i1760�`1829�j�Ɏt�������������w���C�߁A�܂��o�~�A♁A�ɂ������A�����ւ̑��w���[�������B��́A�͂��ߋ��q���˂Ɋw�сA���˖v��A����̓n�ӛ��R�ɓ���A�܂��J����ɂ��w�ԁB����c�̉敗�Ɏ��i���A�v���@�ӂƂ��āA���邢�F���̉ԙ���y�ћ��R����̏ё���ӂƂ����B���a�Œ��`�ɓĂ��l���ł������Ƃ����A���R�ɐ[���M�����ꂽ�B���R�̓��S�E孋��̍ہA�~���ɓw�߁A���R�v��͂��̈⎙�~�i���j�̗{����ʂ����Ă���B��l�ɂ́A�n�ӏ��A����H�J(1827�`1898�j�Ȃǂ�y�o���A�u���n�v��Ƃ̔͂ƂȂ����B
�� ���c�����@�������N�i1804�j�`�������N�i1864�j
���͘ɁA���͋g�l�A�ʏ̋��O�Y�A����A���ցA�������Ƃ��̂��B���B�֓c�S���t�i���֓c�s�j�̏o�g�ŁA�ŏ��|��˂̌�p�G�t�����ȍO�i1772�`1839�j�ɂ�����A�V�۔N�Ԃɍ]�˂ɏo�ě��R�ɂ����B�؎Ђ̍���A�c����孋����̛��R��K�ˁA���̕n������Q���A�`����������B���̋`����R�ɑ���˓��O�̐��]���ĂсA���R�͎��n�̓���I�Ԃ��ƂɂȂ�B�Ԓ��R����������悭�������A�֎R�̕`���Ԓ��ɋy�ʂƍl���A�R����𑽂��c�����B�����R�N�i1856�j12������S�Ă���ƁA���T�N�Q���܂ō����̓c���˓@�ɉ��Z�܂����A�ˎm�ɉ�̎w�������Ă����B�ӔN�]�ˍ��݂ɉB�������B�����͛��R�̎��̌����ɂȂ������Ƃ����ӂ��A����̎���́A�n�ӉƂ̕���ΐ�P�Y���ɑ���悤�⌾�����B
�� ���䌰���@���a�Q�N�i1802�j�`�����R�N�i1856�j
���]���Y���S�ɍ��_�̉Ƃɐ��܂ꂽ�B�c���͌����Y�A���͜y�A���͋ԕv�A���͌��ցA40�����O�J�E�O�J�R���Ə̂����B����剺�Ŋ|��˂̌�p�G�t�����ȍO�i1772�`1839�j�ɓ��債���B�Z�����Y�̖v��A�Ɠ��p�������A26�ō]�˂ɏo�āA�J����̖�ɓ���B������u��R�ʐ��O�v�̍������������B�A����A�V�ۂU�N�i1835�j�Ăэ]�˂ɏo�ě��R�ɓ��債���B�t���R�̍�i��O�O�ɖ̎ʂ��A�R������ł����ӂƂ����B�n�ӛ��R���`�����w�|�W�}�x�i�d�v�������E�ÉÓ����ɑ��j�͌��ւɑ���ꂽ���̂ł���B
�� ���c莆���@�����Q�N�i1805�j�`�O���R�N�i1846�j
���{�ː쎁�̉Ɛb�ō]�ˋ�����{�V��ɏZ�݁A���͏d��A���͎m���A�ُC���Ƃ������A�ʏ̂𐴉E�q��Ə̂����B��R�Ɋw�сA�֎R�Ɠ��l�ɎR���Ԓ��ӂƂ������A������i�����Ȃ��B���R���؎Ђ̍��ŕ߂���ƁA�֒֎R�i1801�`54�j�Ƌ��ɋ~�ω^���ɖz�������B���ȓ��̋L�^����R�{琹�J�i1811�`73�j�ƂƂ��ɁA�֎R���M����u�����F�l�̂ЂƂ�ł��邱�Ƃ��킩��B�O���R�N�V���T���A����̕������F�J�h�ŕa�v�����B�ߔN�A莆��Ɋւ�鎑����������B�c���s�����قɎ�T����\��������`�m������܂Ƃ߂Ċ��ꂽ�i�c���������ٔN��攪���Ɉꕔ�Љ�j�B�܂��A���m�������c����n��ɂ���R�Ԃ�莆�쌴��Ǝv���鐅���������邱�Ƃ��킩�����B���ꂩ��̌�����҂�������Ƃ̂ЂƂ�ł���B
�� �����t���@�������N�i1818�j�`�����T�N�i1858�j
�����Ǐ��i1785�`1840�j�̒����Ƃ��č]�ˏ��ΐ�@���Ő��܂ꂽ�B���͏t�q�A�������X�B�c�����畃�ɊG���w�сA�̂�14�A5�ś��R�Ɏt�������Ɠ`������B�V��14�N(1843)����17�N�ԁA����ˏ\���ˎ�O�c�đׁi1811�`84�j�̕v�l�n�P�Ɏd�����B���U�Ɛg��ʂ����B���Ղɂ������A�����Ŏʎ��I�ȊG��`�����B���R�ƕ��Ǐ��̉e�����A�C�i���������i��������B
�� �֓������@����11�N�i1814�j�`�����R�N�i1870�j
��썑�Ζ쑺�i���Q�n�������s�j�ɑ㊯�֓��s�V�i�i��V�i���g�p�j�̎O�Ԗڂ̎q�Ƃ��Đ��܂��B���Z�`���q�A���Z�`�O�Y�ƎO�Z��B���͐��Z�A�������ʁA�ʍ��ɒ�����B���͌�]�˂Ɉڂ�A���{��q�d����̗p�l�ƂȂ����B���ʂ͏\�ŕ��ƒm�Ȃł��������R�ɂ��A�؎Ђ̍��ł́A�����Ƃ��t�̋~�ω^���ɖz�������B�c���̍������{�Ƃ��Ė̎ʂ��Ă������R�̉�@�𒉎��Ɍp������������q�ł���B���R����c���H�����ɍ֓��ƂɈ��Ă��莆������A�֓��Ƃƛ��R�Ƃ̌�V���m����B���{�������Y���Y�ɉł��A��l�̎q�����������B���R�v��́A�J����i1763�`1840�j�̒�q�ŁA�F���ˈ�ɉƂɎd���A�@��ƂȂ������|�i�C�i1803�`74�j�ɓ��債���B������̍�i�͍��Ɏc����̂����Ȃ��B
�� �i�����R�@�����R�N�i1820�j�`���v�Q�N�i1862�j
�i�����R�͖��{�̗S�M���J��P���Y�̎O�j�Ƃ��č]�ːԍ�ɐ��܂ꂽ�B�c�����O�Y�A�ʏ̂͐W�g�A���͊��A���͍ϖҁA���͎��R�A�̂��Ɉ��R�Ə̂����B���R�͛��R�̓��L�w�S�y�����^�x�i���m���w�蕶�����A�l���j�̕���13�N11��6���̍��ɏ��߂ēo�ꂷ��B���̎��A11�ɂȂ�B���̍��̛��R�͖�����ƘZ�̂����ɉ�m���J���Ă��āA���̉�m�Ɉ��R�͒ʂ��Ă��Ă����B�V�ۂX�N�i1838�j19�̎��A�㊯�H�q�O�L�i1790�`1862�j�̈ɓ����������ɎQ�����A���m�Ȓn�}�Ɣ������ʐ��}��`���Ă���B���R���؎Ђ̍��ŕ߂�����ƁA���R�͍]�˂�����A�����𗷂���B��\�Α�̒����l����������m���Ă��邪�A�i���𖼏��̂́A�Éi���N�i1848�j29�ŋ��J�h�̑g���E�i���Ƃ̖��{�q�ɓ����Ă���̂��Ƃł���B�ȗ��A�g���̎d���藧�āA�M��u�������A��N�A�R�{琹�J�̖������A��Ƃ��u�����A�]�����Ⴍ���ӂ̔ӔN���߂������B�Ⴍ���Ďt�ł��雺�R�ɉ�Z��F�߂��Ȃ���A�[���ɔ����ł����ɐ��U���I�����B
�� �n�Ӕ@�R�@����13�N�i1816�j�`�V��8�N�i1837�j
�@�R�͛��R�̖���Ƃ��č]�ˍ����ɐ��܂ꂽ�B���͒�Łi�������Ɓj�A���͋G�ہA�ʏ̂͌ܘY�A�@�R�܂��͉ؒ��ƍ����B�Z���R�̊��҂ɉ����A�w��������������A���������҂��ꂽ���A22�ő��������B14����֒֎R�i1801�`1854�j�̉�m��ؓ��ɓ��債�A�Ԓ���ɂ͛��R�E�֎R��l����̉e����������B�V��7�N���s�́w�]�ˌ��ݍL�v���Ɛl���^�x�ɂ́A���R�ƕ���Ōf�ڂ���A��l�Ƃ��Ė��𐬂��Ă������Ƃ��M����B����4�N�i1821�j���R29�̎��̃X�P�b�`���w�h����e�x�ɂ�6�̗c�Ȋ�́u�ܘY���v�Ƃ��ėL���ł���B
�� �։ؒJ�@�����W�N�i1825�j�`�Éi�R�N�i1850�j
�֒֎R�̒��j�Ƃ��Đ��܂�A�����P�g�Ƃ������B�֎R�����R�̒�@�R���q�ɂ��Ă����悤�ɁA�c�����ĉؒJ�͛��R�ɓ��債���B�ؒJ�Ƃ�������15�ŗ^����ꂽ�ƌ����Ă���B�@�R�����R�Ƌ��ɓc���ˎ�O��N���i1811�`1893�j�̓������s�ɐ��s������Ĉ�l��������ƁA�ؒJ�͒֎R�̓���ׂ��l���ł������B���R�̗F�l�ŔԒ��̊w�Ғ������̖����ȂɌ}���A�ꏗ�����������B�c�O�Ȃ���A�֎R�ɐ旧���A26�ŖS���Ȃ����B
�� �n�ӏ����@�V�ۂU�N�i1835�j�`����20�N�i1887�j
���͛��R�̓�j�Ƃ��č]�ˍ����ɐ��܂ꂽ�B���R���S���Ȃ������ɂ͂킸���ɂV�ł��������߁A���R����̉e���͑����Ȃ������B���̌�A�O���S�N�i1847�j13�̏��͓c������]�˂ɏo�āA�֒֎R�̉�m��ؓ��ɓ��債�A�֎R�̎w���ɂ��A�Ԓ���̋Z�@���K�������B�]�ˍ̒��Z����25�ŖS���Ȃ������߁A�n�ӉƂ̉Ɠ𑊑����A�����̓c���˂̉ƘV�E��A�p�ˌ�͎Q���̗v�E���߂��B�Ԓ���ɂ́A�Ǝ��̐��E��z���A�{�����i�����{�a�j�ɐ��ˊG���c���ȂǁA���O�͂≓�B�̍�Ƃɑ傫�ȉe����^�������A53�ŕa�v�����B
�� �n�Ӊؐ��@�Éi5�N�i1852�j�`���a�T�N�i1930�j
���É��ɐ��܂�A���͏���×Y�A�ፁ�A�É��ƍ������B����10�N(1877)���A�����S�����ɏ��L�Ƃ��čݔC�B���n�ӏ��Ɏt�����܂����B����15�N�A�����㋞����ƁA���E�������A�����ɏo�܂����B����17�N�A��2������G�拤�i��ɏo�i�B����20�N�A���̖v��A�n�Ӑ��𖼏��A�ؐ������A���n�̊Ӓ���悭�����B
�� �֓�R�@����6�7�N�i1873�74�j���`����39�40�N�i1906�E07�j
�֎R�̑��ŁA���͑��������ؒJ�ɑ���Ɠ𑊑������֎R�̎l�j�֘a�g�ł���B�֎R�̉�m��ؓ����p��������H�J�i1827�`1898�j�Ɋw�B��������O���ɁA���E����̒x������߂����Ɨm���������i�߂����{�ł͓`�����p�͐��S�����B���{�ŗL�̔��p�̕������͂��邱�Ƃ�ړI�Ƃ������{���p����ł��A���p�W��������I�ɊJ�Â��A���{�̔��p�E�̒��S�I���݂ł������B���̓��{���p������p�W����ŁA����27�N�w���ԙԌ{�}�x�ŖJ��ꓙ���A��28�N�w�r������}�x�ŖJ��A��29�N�w�|�����{�}�x�ŖJ��ꓙ�A��30�N�w�b��}�x�ŖJ��ꓙ�A��31�N�w���{�}�x�ŖJ��ꓙ�A��33�N�w�H�x�R�{�}�x�ŖJ��O���A��35�N�w�����c���}�x�ŖJ��ꓙ�A��36�N�w�~�ԟ����}�x�ŖJ��ꓙ����܂��Ă���B���u��R�v�͗H�J���疾��30�N6���ɗ^����ꂽ�B�w�ߊ�k�}�x(�c���s�����ّ�)�́A����H�J�̉�m�a�y���̗l�q�����������m����M�d�Ȏ����ł���B
�� ���ьj���@����9�N�i1876�j�`���a38�N�i1963�j
���ьj���́A�R�����E���s�ɐ��܂�A�����ɏo�ēn�ӛ��R�̑���q�ɂ��������H�J�Ɏt���A���k�Ŋi�������\�����w�т܂����B���{���p����W�A���W�ɏo�i�B��W�̐R�����A�鍑���p�@����A�鎺�Z�|���ƂȂ�܂����B���A���{���p��������B�����̋��{���������A���E���E��̑S�Ă��D��Ă���Ƃ������n��ڎw�����l��|����`���A���n��ɂ����ẮA���̓Ɠ��̏���I�ȍ앗�������]������A���a33�N(1958)�A�����M�͎�܁B�����͈ɓ��B�{���͓āB��\��ɢ�t���ԉe��ȂǁB
�� ���ѐ���@����11�N�i1878�j�`���a44�N�i1969�j
�����͔ˎ叼�э����̖��Ƃ��ē����ɐ��܂ꂽ�B���ьj���̍ȁB���͍F�q�B����H�J�Ɏt�����A�Ԓ���ӂƂ����B���͗H�J�̉�m�œ���ł������j���Ɩ���34�N(1901)�����B�H�J�ɂ������Ԃ͖�2�N�ł��������A���n�̕`�@����X�܂œ`�����B������́A�W����ւ̏o�i���قƂ�ǂ����ɁA�j���̎x���ɐs�͂����B
�� �n�ӛ��R�@�O�g�u
���{��Ƃł��鉺���ώR(�P�W�V�R�`�P�X�R�O)�����i�ł���B�O�g�̔u�Ƒ�����琬��B�u�ɂ͛��R�̉悪���i���j���N�����i���j䉖�i��j�������ɕ`����Ă���B����͊ώR����ł���B�����ɂ͢�����l�̈˗���Ƃ���B
�� ���|��@�ݗ����]��
�u�ݗ����]�@��Љē��@�|��Վm���v�Ƃ���A�镶���`��́u�|��v��悷�B
�u�ݗ��v�Ƃ͋ɂ߂ĉ��������̂��Ƃł���B�w�����I�R�`�x�ɂ́u���V����A���������v�Ƃ���A�V�������ꂳ��A�ɂ߂ĉ������܂ł��A���������ɂȂ�Ƃ����Ӗ�������B�u�����v�Ƃ������t�ɂ́A���얋�{�̐����疾������ɓ���A���̒������肵�A�ו��ł��邱�Ƃ�\�������̂ł��낤���B�|�킪�Ɛb�Ƃ��Ă������{�ː쎁�͖��b�ł���A�����ېV��A����Ƃ��x�{�E���B�ɓ]�����ꂽ���Ƃɂ��A�]�˂𗣂ꂽ�B�ː쎁�̋��R���~�����|��ɂ́A���삩�疾���̎���ɕς��s�����̒���S�ە��i�Ƃ��ĕ`�����������̂ł��낤�B��O�̗��n��\���X�ƑΊ݂̘A�R�������D�́u���m�v�ւ̋��D���B
�� �����ؗz�@����t�����
��ʂ̎R�܂�J�܂�̉��ʕ����ɊG��s���R�ɒ��F���ꂽ�Ƃ낪����A���ɍ�������ꂽ��q�ɒ��ڕM����ꂽ���̂ł��낤�B�u����t���@�Ȉ�ܗz���@�ؗz�R�l�v�Ƃ���A�g�~�̎}�ɂƂ܂鉍�𒆐S�ɖ��̗t�F������ɕύX���A�I�݂Ɏg�������Ă���B
�� �勴���@�_�Β�
8�}���Ȃ鐅�n����Ƃ����撟�ł���B�Ԃ���f�̎��ɒW�����F���邪�A�}�t�͑S�Ėn�̔Z�W�ŗ��̊���\�����Ă���B�ז��Ȗѕ`���̌ՂӂƂ��Ă������ł��������A��{�I�Ȑ��n�\�����[���Ƀ}�X�^�[���Ă��邱�Ƃ��킩��B�撟�̑莚���땶�́A����10�N��̎Ⴂ���ɉ���w��_�̌˓c�ܓ��i1851�`1908�j�ł���B
�� ����H�J�@�ԙ���
�ŏI�}�̗����Ɂu���яt���ʈד��t��N�@�H�J���v�ƋL���B�莚�u�S�a���V�^�v�������������J�i1835�`1920�j�͌��R���ˎm�ŁA�ېV��͋{���Ȃɋ߁A���ƂƂ��Ă����A�q�݂ƂȂ�B���㕗�ɓǂ߂A�u�S�a����A�V�^��v�ŁA���_�͗����́u��漳�̖��{�Â���ɑ���v�Ƃ�����̊����̈�߂ł��B�S���a�炰�A�l�Ԗ{���̎��R�Ȏp�ł�����A�Ƃ����Ӗ��ł���B�H�J�͖���15�N��17�N�ɊJ�Â��ꂽ��P��E��2��̓����G�拤�i��̐R�����߁A��͂�F�߂�ꂽ����̍�i�ł���B���O�A���ɗ�ŁA��ƍ��A���ɉ��A�ɐ��C�V�ƃT�U�G�E�A�T���A�@�ɐ�A�I�ƃn�}�O���E�c�u�L�A�G�Ƌe�A�e�A���A�ւƗM�q�A�ᒆ�~�ɐ��A�~�ɐ����12�}�̏��i�ł��邪�A���n�̉Ԓ���Ƃ炵���������̂����i�Ɏd�グ���Ă���B
�� ���D�@��C�C�g�ɐ��啶�l�@�����n
�L�ɕ�������(�Ђ炫��ς���)��D����ꂽ�B�d�X�������̑����B�o���������Ēi�ւ�Ƃ���Ƃ��납�炢���铷���̐�C�C�g���A���̐F���Ɍ�����B��ւ̐C�g�Ƃ������A�������ӏ��̍l�Ă̎��ɂ́A�����t�̐�̈�ʂɍ~��ςl��\�����悤�Ƃ����̂ł��낤�B���������y���̂��������킯�Đ��^�Ȑ��傪�B�Ԃ�t�̂����Ȃ�łȂ������ɒ��ڂ����B
�� �n�ӛ��R�@���A�}
�W�̉�㺔V���A���D�B�R�A�ɂē��҂̎����A�����Ĕ������Ǝv�����B���҂͉�㺔V�Ɍ������B������o�������Ă�������A�����A�ƌ����������܂��傤��ƁB��㺔V�͊��ŏ��������ė^���A�A���B���̐}�͂��̌̎��i��㺔V�`�j�̏�ʂ�`�������̂ł���B��i�A���̌��ɍ���͉̂�㺔V�A���i�A�A�����Ă���͓̂��҂ł���B�����͑����̉؎R�ł���A27�A8�̍��̍�i�Ǝv����B
�� �n�ӛ��R�@�n���}
���Ɂu�ߐΑa�ԑ��@�ѕ��חt���@��Ϗ���@���ᖞ沅�Áv�A�����́u�����h�v�Ƃ���A�镶�T�b��́u�o�v���悷�B�ǂ݂́u�ɘ߂��đa�ԑ����A����тčחt�����B��ς̏�����A����沅�Âɖ��v�ƂȂ�B��ς͐퍑����̑^�̐l�ŁA�����i�O343���`�O277���j�̎��ł���B�^�̉����ɐ��܂�A���̑��߂Ƃ��Ċ������A�i�܂�Ď��r�A沅���̂قƂ�ŗ�������Đg�ɕt���A�����i�ׂ���j�ɓ��g�����B���̍����ȋ����̂��Ƃ𗖂ɓY�������̂ł���B�V��10�N�i1839�j�ɂ�͂肱�̎���Y������i�u���|�o���v������B
�� ���䌰�ց@�����P���V�}
�P���͌×������ŁA�i�فE�T�E���Ƌ��Ɏl���Ƃ��đ��ꂽ�z����̐����ł���B�`�́A�O���i�فA��͎��A��͎ցA�{�͌{�Ɏ��A�ܐF��ࣁA�Y��P�A���Ƃ����B�����͒��z�̂��ƂŁA��������g�����ł���B�g�͒J����i1763�`1840�j�E�֒֎R�i1801�`54�j�ɂ��ޗႪ�����A�P�����܂߂āu�}���v�ƍl�����邪�A���̕M�v�͒��J�ŁA�ז��`�ʂɌ��ւ̉�͂̏[���Ԃ肪�M����B�����ɂ́u�ȓє��H���@���֜y�v�Ƃ���A�Éi2�N7���̊����ł��邱�Ƃ��킩��B�V��12�N�̏��ȂŁA���R�����ւɂ��Ď��̂悤�ɏq�ׂĂ���B�u���l��ɖނ������A���O���ɂĂ��o���\�������̖����v�l�\�Ŋ��ɂǂ̂悤�Ȏ��A�M�@�ɂ��Ή��ł����悤�ŁA���������đ����̈˗���Ƃ��ĕ`������i�̂ЂƂł��낤�B
�� �����t���@���ߔV�}
���͎�������t�̐F��ς��Ȃ��Ƃ��납��A�ߑ��E�����Ȃǂ̏ے��Ƃ����B�܂��A�߂͎p�A�����Ƃ��ɋC�����A��N�̒�����ۂ��Ƃ��đ����B
�� �֓����ʁ@��i�R���}
�Â��ȋ�C���������ł���B�w�i��n�œh�邱�ƂŁA�~�̐�̓������X�Ɠ`����Ă���B�O�i�������p�ɊA�E����J�����ĉ��R���݂���\�}�́A�k�@��̊G��ɋ߂��ł��낤�B
�����͢������č��ʏ�����Ƃ���A5���ɕ`���ꂽ�B
�� �i�����R�@���v�}���
�����M�𑖂点�����ł���B�����͢�h�яH�����R���ӣ�B���v���N�i�P�W�U�P�j�A�S���Ȃ�P�N�O�̍�i�ł���B
�� �n�Ӕ@�R�@���ĎO�F�}
�P�V�A�W���̍�i�Ǝv����B�S���g�A�@�A���̉ċG�̉Ԃ�`���B�����đ傫�ȉԁA�@�𒆐S�ɂ��āA�㉺���E�ɐA�����z�u����Ă���B
�� �։ؒJ�@���O�q��L�}
�S���Ȃ�O�N�̍�ŁA�����ȃR���N�^�[���c�Ƃ̑��i�ł������B�L�͖n�̓h��c���̒��ɑ̂�я������A�_�炩����\�����Ă���B
�� �n�ӏ��@����ꐆ�}
�����R�̐�M�ł���}����ɕ`�������̂���������B�����R�́u�o�v�u���R�v���悵�Ă���B���̍��ɏ��̗����u�Ƒ�����ꖲ�}�Ɖ���M��������l���ݔV���p�ߐV��ܓ�����~�v���L�����B�}���^�́A���R�̐�M�Ɠ`�������i���璉���Ɏʂ��A�u�C���o����@絒���Ḑ��n���@���Ȗ��@�����o���ȗ��t�@�q���ȗC�@�N�]���\�@�y���C���d�@������P���n�@�ڍ݈ٕ��^�@����嫋ߖϒa�@�x����[��@�̕x�M�Ҕ\�m�V�@���s�M遉h袪�~�V�K�@������z���V���@�����Տ]�@�n�ˎҔ\�m�V���@�s���ڋ������V�O�@�����㎩��m���@�����Ոׁ@��F���҈ꐆ�V���@�֊��ꐢ�@�s���s�G�ϓ��ϑz�@��v����@���L�V�@�q���v�Ƃ���B�G�̍\�}�ł́A���R��i�̉�������������悤�ɍ\�����A�w��ɂ����藧�R�⌯�����R�A���S�ɗ����Ȃǂ́A�����R�̐�悤�ȋْ�������������̂��A�`����Ă��Ȃ��B
�� �֓�R�@���o���V�}
���ɂ������ފ��Ƃ��̉A�ɂ�����H�̊���`���B��ʍ��Ɂu�b�C�ē����@�֓�R�v�Ɨ���������B���{���p������p�W����ŘA�����ĖJ�����܂�����͂�����������B�ߌi�ł����O�̔������Ɗ�A�����ɐL�т�|�̉��ߊ��̉��s�\���̉��o�͑c���֎R���v���N��������B
�� ���ѐ��@���Ԑ}
�ォ�牺���ꉺ���铡�̉Ԃ�`���B��ʉ��ɂ͗]��������ċ�Ԃ̍L��������o���Ă���B�O�N11���ɂ́A�h�{���菬�w�Z�s���ɕv�j���́u�x�m�v�Ɛ��́u����ԁv���f���A���a30(1955)�N�ɂ͓c����(���c���s)�̛��R��v���̓V���Ƃ��āA�j���́u�n�|�v�A���́u���O�v����i���Ă���B���͓W����o�i�͍T���Ă������A���̍��͕v�Ȃō�i����ׂēW�����邱�Ƃ������������̂ł��낤�B