![]()
![]()
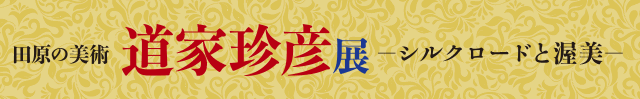
| �J�� | �F | ����28�N3��26���i�y�j�`����28�N5��15���i���j
�E�O���W���F3��26���i�y�j�`4��17���i���j�܂� |
|
|---|---|---|---|
| �J�َ��� | �F | �ߑO9���`�ߌ�5���i���ق͌ߌ�4��30���܂Łj | �� �W�����ڍׂ͂����� |
| ��� | �F | �c���s������ |
| ���W�����P | ||||||||
| ������i | ||||||||
| No. | �}��No. | ��i�� | ����N | �ގ��Z�@ | �`�� | �o�i�� | ���� | ���l |
| 1 | 1 | ������ | 1951�N | ���{���� | F�T�O | ���ƒ��F | ||
| 2 | 3 | ���i | 1953�N | ���{���� | F�U�O | ���ƒ��F | ||
| 3 | 4 | �h�B���H | 1967�N | ���{���� | F�U | ������@ | ����W�� | |
| �V���N���[�h | ||||||||
| No. | �}��No. | ��i�� | ����N | �ގ��Z�@ | �`�� | �o�i�� | ���� | ���l |
| 4 | 5 | �p�� | 1970�N | ���� | ���� | �W | ���ƒ��F | |
| 5 | 6 | ���� | 1974�N | ���{���� | ���F�曠�� | ������ | ||
| 6 | 8 | ���l | 1977�N | ���� | ���� | ��16�ی`�ۓW | �����a������Ёi�{�揊���j | |
| 7 | 9 | �p�k���䂭 | 1980�N | ���{���� | �Z�ț��� | �W | �������y������ | |
| 8 | 10 | ����A�i���̊C�j | 1980�N | ���{���� | �Z�ț��� | �W | ���ƒ��F | �O���W�� |
| 9 | 11 | ����B | 1980�N | ���{���� | �Z�ț��� | �W | ���ƒ��F | ����W�� |
| 10 | 12 | �������䂭�i�p�k���䂭�j | 1980�N | ���{���� | M�R�O | �l | ||
| 11 | 14 | �[�������т� | 1980�N | ���{���� | M�R�O | ��16�m��W | �l | |
| 12 | 17 | �s���~�b�h | 1983�N | ���{���� | ��ț����~�Q | �W | ���ƒ��F | �O���W�� |
| 13 | 19 | ��-�p�s�E�g���t�@�� | 1983�N | ���{���� | F�P�Q�O | �W | �������y������ | |
| 14 | 20 | �z | 1983�N | ���� | ���� | �W | ���ƒ��F | |
| 15 | 21 | �V�R�z | 1984�N | ���{���� | F�T�O | ��10��S����W | �������y������ | �O���W�� |
| 16 | 22 | �������i���������j | 1984�N | ���{���� | ��ț��� | �W | ���ƒ��F | �O���W�� |
| 17 | 23 | �`�����^������ | 1984�N | ���{���� | F�Q�O | �l | ||
| 18 | 24 | �p�k���䂭 | 1984�N | ���{���� | ��F�R�O | �^���O | ||
| 19 | 27 | �V�R�z | 1985�N | ���{���� | F�Q�O | �l | ||
| 20 | 28 | �`�x�b�g���� | 1985�N | ���� | ���� | �W | ���ƒ��F | |
| 21 | 30 | �p�k���䂭 | 1985�N | ���{���� | ���F�曠�� | ������ | ||
| 22 | 32 | �o�[�~�����k�J | 1986�N | ���{�n�� | �Z�ț��� | ��22�m��W | ��� | |
| 23 | 35 | �p�s�E�V���N���[�h | 1987�N | ���{���� | F�S�O�O�iF�P�O�O�~�S�j | �W | ���ƒ��F | �O���W�� |
| 24 | 36 | �p�s�E�c�� | 1987�N | ���{���� | F�S�O�O�iF�P�O�O�~�S�j | �W | ���ƒ��F | ����W�� |
| 25 | 37 | �p�s�i�A�t�K�j�X�^���j | 1987�N | ���{���� | F�P�O�O | ��9��R����p�ُܓW | ���쉮���� | |
| 26 | 39 | �c�� | 1987�N | ���{���� | F�U | �������y������ | ||
| 27 | 40 | �V�R | 1987�N | ���{���� | P�R�O | �������y������ | �c��������� | |
| �V���N���[�h | ||||||||
| No. | �}��No. | ��i�� | ����N | �ގ��Z�@ | �`�� | �o�i�� | ���� | ���l |
| 28 | �| | �V�R�z | 1987�N | ���� | ���� | ���ƒ��F | ||
| 29 | �| | �V�����S���S���@�����苃���̋u | 1988�N | ���{���� | �e�Q�O�O | ���ƒ��F | ||
| 30 | 41 | �A�H | 1988�N | ���{���� | F�Q�O | �L����������W | �l | |
| 31 | 43 | �V���N���[�h | 1990�N | ���{���� | �G�z | �W | �A���� | |
| 32 | 44 | �y���Z�|���X�z | 1990�N | ���{���� | P�R�O | �l | ||
| 33 | 48 | �����̏� | 1996�N | ���{���� | P�R�O | �l | ||
| 34 | 49 | �� | 1996�N | ���{���� | F�S | �������y������ | ||
| 35 | 50 | �œV�L�����o�� | 1997�N | ���{���� | �G�z | �l | ||
| 36 | 51 | ��V�} | 1998�N | ���{�n�� | �ςP�O�O | �W | ������ | |
| 37 | 54 | 㳓����� | 2000�N | ���� | ���� | ��36�m��W | ���ƒ��F | |
| 38 | �| | �A�t�K�j�X�^���E�V�����S���S���@�Θb | 2004�N | ���{���� | F�P�O�O�~�Q | ��40��L�O���m��W | ���ƒ��F | ����W�� |
| 39 | 58 | �������i�p���R���E�`�����f�j | 2006�N | ���{���� | M�R�O | �W | �����V�[�����O���(��) | |
| 40 | �| | �n�g�V�F�v�X�g�Ց��a�i�G�W�v�g�j | 2010�N | ���{���� | F�P�O�O�~�Q | ��46�m��W | ���ƒ��F | �O���W�� |
| 41 | 72 | �G�W�v�g�E�s���~�b�h | 2012�N | ���{���� | F�R�O | �l | ||
| 42 | 74 | ���O�ʊy�l | 2013�N | ���{���� | F�U | ���Ԉ�@ | ����W�� | |
| ���i�i���E���g�O���t�E�X�P�b�`�Ȃǁj | ||||||||
| No. | �}��No. | ��i�� | ����N | �ގ��Z�@ | �`�� | �o�i�� | ���� | ���l |
| 71 | �| | �V���N���[�h�@�L�����o�� | 2014�N | ���g�O���t | SM | ���ƒ��F | ||
| 72 | �| | �y���V���̗z | 1998�N | ���g�O���t | SM | ���ƒ��F | ||
| 73 | �| | �y���Z�|���X | 1997�N | �X�P�b�` | SM | ���ƒ��F | ||
| 74 | �| | �` | 2014�N | �X�P�b�` | �O�� | ���ƒ��F | ||
| 75 | �| | �R���q�i�����Ȃ��j | 2014�N | �X�P�b�` | �O�� | ���ƒ��F | ||
| 76 | �| | �����E���� | ���{���� | �Z�� | ���ƒ��F | |||
| 77 | �| | �����E�q�����b�g�V�[�h���X | 2013�N | ���{���� | �Z�� | ���ƒ��F | ||
| 78 | �| | ���|�E�N�C�[�� | 2014�N | ���{���� | �Z�� | ���ƒ��F | ||
| 79 | �| | �X�`���[�x�� | 2013�N | ���{���� | �Z�� | ���ƒ��F | ||
| 80 | �| | �؎q�q�i�C�����o�y�j�K���X�@�S�`�UC | �X�P�b�` | �F�� | ���ƒ��F | |||
| ���W�����Q | ||||||||
| ���� | ||||||||
| No. | �}��No. | ��i�� | ����N | �ގ��Z�@ | �`�� | �o�i�� | ���� | ���l |
| 43 | 77 | �ɗnj�酉J | 1993�N | ���{�n�ʉ� | �l�ț��� | ��29�m��W | ���ƒ��F | ����W�� |
| 44 | 78 | �C�� | 1994�N | ���{���� | �l�ț��� | ��30�m��W | ���ƒ��F | |
| 45 | 79 | �ɗnjΐ����@�[�� | 1994�N | ���{���� | F�P�Q�O | ���m�����30��L�O���ʓW | �������y������ | |
| 46 | 80 | �ɗnj@�z | 1994�N | ���{���� | F�Q�O | �c���s������ | �O���W�� | |
| 47 | 81 | �z���i���R�u�̒�q�j | 1995�N | ���{���� | �l�ț��� | �W | ���ƒ��F | �O���W�� |
| 48 | 82 | ��� | 1995�N | ���{���� | ��ț��� | ������ | ||
| 49 | 83 | �ɗnjΕ��i | 1995�N | ���{���� | ���G�i�S���j | �l | ||
| 50 | 84 | �ɗnj@�_ | 1995�N | ���{���� | F�Q�O | �l | ||
| 51 | 85 | �ɗnjΎ��J | 1996�N | ���{�n�� | �l�ț��� | �W | �㉤�� | �O���W�� |
| 52 | 87 | �o�q | 1996�N | ���{���� | F�Q�O | �W | �쐣��@ | |
| 53 | 88 | ���� | 1996�N | ���{���� | F�Q�O | �l | ||
| 54 | 89 | ���@�ɗnj� | 1998�N | ���{���� | �l�ț��� | ���ƒ��F | �O���W�� | |
| 55 | 90 | �ɗnjΕ\�l | 1998�N | ���{���� | �G�z | �l | ||
| 56 | �| | �ɗnjΐ����@�U�i�^���J�[�j | 1998�N | ���{���� | F�P�O�O | ��34�m��W | ���ƒ��F | ����W�� |
| 57 | 86 | �ɗnj@�_�i�ɗnj@99�j | 1999�N | ���{���� | F�T�O�~�Q | ��35��t�G���m��W | ���ƒ��F | �O���W�� |
| 58 | 91 | �t�ɗnj@���D | 2000�N | ���{���� | F�Q�O�O | �����V�[�����O���(��) | ||
| 59 | 92 | �ɗnjΓ��� | 2002�N | ���{���� | F�Q�O | �W | �l | |
| 60 | 93 | �ɗnjΓn�� | 2002�N | ���{���� | �l�ț��� | �쐣��@ | ||
| 61 | 95 | �ɗnjΓn�� | 2002�N | ���{�n�� | �� | �㉤�� | ||
| 62 | 96 | �ɗnjΓn�� | 2003�N | ���{�n�� | �G�z | �W | ���� | |
| 63 | 97 | �ɗnjΎ��J | 2005�N | ���{���� | ��ț��� | ���m�����30��L�O���ʓW | ���ƒ��F | �c��������� |
| 64 | 98 | �ɗnjΐ����@�_�� | 2008�N | ���{�n�� | �G�z | �W | �l | |
| 65 | 99 | �ɗnjΓ��� | 2011�N | ���{���� | F�R�O | �l | ||
| 66 | 100 | �ɗnjœV | 2013�N | ���{���� | F�R�O | ��28�i�̉�G��W | ���ƒ��F | ����W�� |
| 67 | 101 | �ɗnjΓn�����i | 2014�N | ���{�n�� | �Z�ț��� | ������ | ||
| ���̑��i�g�ˉ�j | ||||||||
| No. | �}��No. | ��i�� | ����N | �ގ��Z�@ | �`�� | �o�i�� | ���� | ���l |
| 68 | 107 | �œV�x�m | 1995�N | ���{���� | ���F�曠�� | ���쉮���� | ||
| 69 | 103 | ���} | 2002�N | ���{�n�� | �� | �㉤�� | ||
| 70 | 108 | �V���} | 2012�N | ���{���� | �Z�ț��� | ���i�����w�Z | �O���W�� | |
����W��
| ���W�����P�A���r�[ | ||||||||
| �V���N���[�h | ||||||||
| No. | �}��No. | ��i�� | ����N | �ގ��Z�@ | �`�� | �o�i�� | ���� | ���l |
| 81 | 57 | �`�x�b�g�_�㎛�@ | 2005�N | ���{���� | �e�R�O | (��)����t���� | ||
| 82 | 62 | �z�쎛�E�ω���F | 2007�N | ���{�n�� | �ςP�O�O | ��43�m��W | ���ƒ��F | |
| 83 | �n�g�V�F�v�X�g�_�a | 1995�N | ���{���� | �e�R�O | ���ƒ��F | |||
| 84 | ����×z���i | 2013�N | ���{�n�� | �e�R�O | ���ƒ��F | |||
| 85 | �o�[�~�����E���啧 | 1987�N | ���{�n�ʉ� | �Z�� | ���ƒ��F | |||
| ���W�����Q | ||||||||
| ���� | ||||||||
| No. | �}��No. | ��i�� | ����N | �ގ��Z�@ | �`�� | �o�i�� | ���� | ���l |
| 86 | �ɗnjΗ��� | 1994�N | ���{���� | �l�ț��� | ���ƒ��F | |||
| 87 | �ɗnjΗ[�� | 1994�N | ���{���� | �l�ț��� | ���ƒ��F | |||
| ���̑��i�g�ˉ�ق��j | ||||||||
| No. | �}��No. | ��i�� | ����N | �ގ��Z�@ | �`�� | �o�i�� | ���� | ���l |
| 88 | 104 | ���}�i�j | 2015�N | ���{���� | �G�z | ���ƒ��F | ||
| 89 | 105 | ���}�i�n�j | 2015�N | ���{�n�� | �G�z | ���ƒ��F | ||
| 90 | ���q�̎��̉� | 2012�N | ���{���� | �G�z | ���ƒ��F | |||
�����Ԓ��A�W����ύX����ꍇ���������܂��B�܂��W�����͍�i�ی�̂��߁A�Ɩ��𗎂Ƃ��Ă���܂��B���������������B
�J�Âɂ�������
�����́A��̌Ï��̗t���������ĂĂ���B�����Ɛ����������Ă���̂ł��낤�B�A�g���G�̌Â����W�I����u�؉Y(������)�|�V�C�E���|�C��28�x�|���͂R�A�|�C��1018�w�N�g�p�X�J���B�P(����)�t(�����)�|�V�C�E�܁|�C��32�x�|���͂Q�A�|�C��1014�w�N�g�p�X�J���B�͖�(������)���d����܂���c�c�B�v�ƕ������Ă���B���͂��̉����Ȃ���A�������Ǝd�������ė����B���̋�Ԃ����܂�Ȃ��D���ł���B
1966�N�A���������̂Ȃ��u���ؐl�����a���v�֎�ނɂł������`�����X���V���N���[�h�Ɏ��g�ރX�^�[�g�ł������Ǝv���B���ꂩ��50�]�N�Ԃɂ킽���āA�킫�ڂ��ӂ炸�`�������ė������Ƃ��ւ�Ɏv���Ɠ����ɁA�i���ɂ킽���Č�x�����Ă������������X�Ɂu���肪�Ƃ��������܂����v�ƌ���\���グ�����B
���̎�����A�V���N���[�h�ɂ�������ĕ`�������Ă����B�������Ƃ��Ȃ��n���A���̕ۏ��[���łȂ��Ƃ���ւ���ނɍs���ė���ꂽ�̂́A�����Ɛ_�̌���삪�������̂��ƐM���Ă��܂��B���ۂɁA���n�ł̑̌������̊G�̌��_���Ǝv���Ă��܂��B
�ǂ������̃V���N���[�h�ƈ��������Ă��������āA���Ȃ��̖��̎����ɏ����ł������ɗ��Ă�Ɗ���Ă��܂��B
�����m��ψ��@���ƒ��F